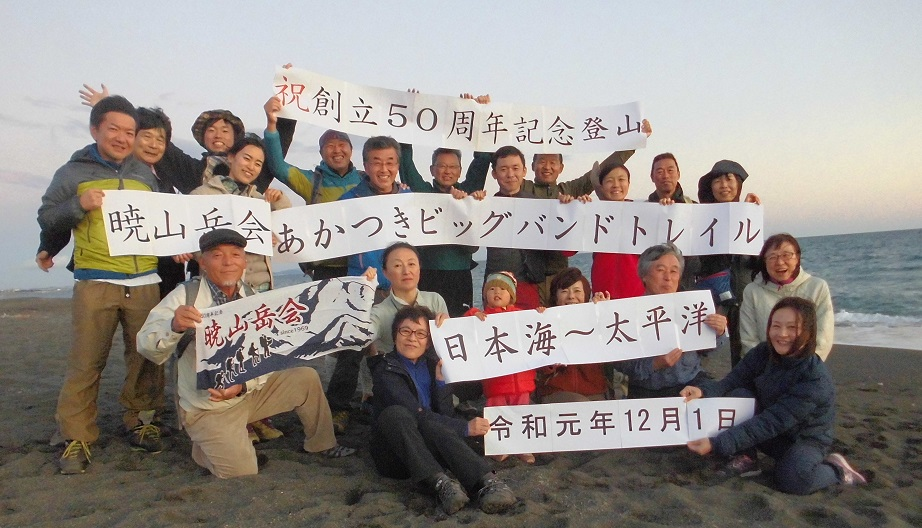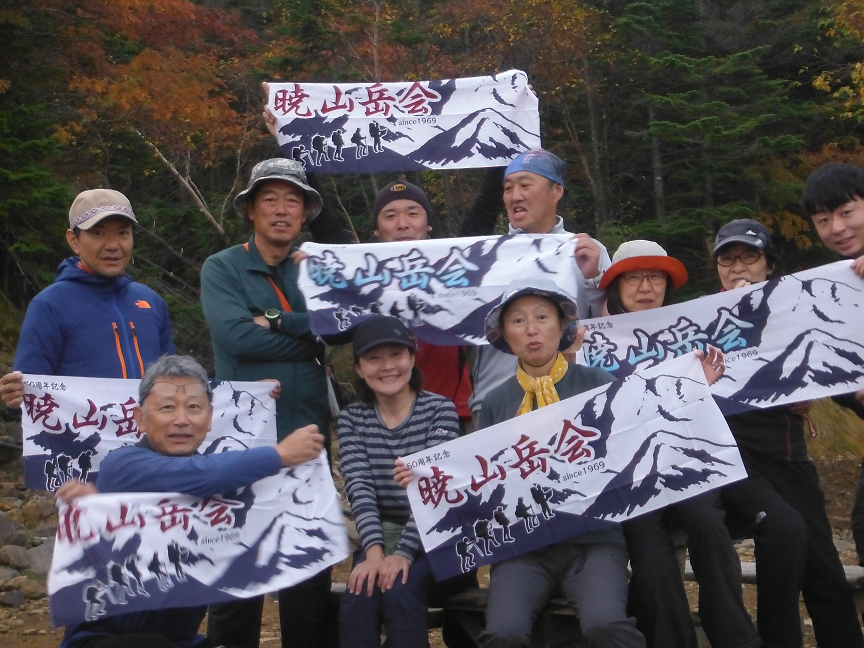期 日:2020年2月8日~9日
参加者:Lなべたけ、ヒー、おとっつあん
2月8日(土)晴れ
相模原=八ヶ岳山荘駐車場(10:20)-美濃戸の氷瀑(10:50~15:00)-赤岳鉱泉(18:00)(幕営)
C隊のコバヤンの車に同乗して、八ヶ岳山荘駐車場に9:30すぎに到着。安曇野在住のヨッシーさんと合流。
登山道入り口から15分ほどの、柳川にかかる橋のたもとから左岸側に1~2分入るとすぐに25mほどの氷瀑がある。C隊のヨッシーさん、コバヤンは、赤岳鉱泉経由で1日で赤岳に登る予定なので、登山道をそのまま進む。
ここの氷瀑は、ルート3本くらい取ることができる。いちばんやさしい左側のルートから登り、トップロープを張って、その後各自3本ずつ登った。


トップロープ用の残置支点あり。右側のルートは、少しだけ垂壁に近い箇所がある。氷の発達は少なく、見た目は心もとない感じだったが、まずまず楽しんで登ることができた。メンバー3名ともにアイスは初心者レベルだが、トレーニングにはちょうど良い氷瀑である。隣の氷瀑は、同様の高さのあるバーティカルアイスで、氷結状況が良いと、登られているようである。この日は未発達で、登るにはかなり厳しそうだった。例年と比べ、氷の発達は良くないようである。温暖化も影響しているのかもしれない。年々厳しくなるような気がする。15:00頃まで氷瀑で楽しみ、赤岳鉱泉へ。C隊と再合流した。
2月9日(日)晴れ
赤岳鉱泉(6:00)-ジョウゴ沢(6:20)-硫黄岳(10:40)-赤岳鉱泉(12:00)-八ヶ岳山荘駐車場(15:00)
赤岳鉱泉を出発して硫黄岳方面の登山道を進む。登山道を横切る3本目の沢がジョウゴ沢で、登山道から入渓する。F1、F2ともに積雪で覆われており、ロープなしで乗り越す。トレースはしっかりあるが、先行パーティーはおらず、後続も見当たらない。大人気かと予想していたが、静かな谷だった。新しい積雪はなさそうだ。分岐まで来ると乙女の滝に取り付こうとしていた2人パーティーに会う。美しいバーティカルアイスで、取り付けたら楽しいが厳しいクライミングになるだろうななどと思いながら、横目で通り過ぎて大滝を目指す。大滝は、左側の下部がえぐられたように崩れていて、右側から登った。私たちが登り始めると、別の2人パーティーが後続してきていた。落ち口右側にハンガーのビレイ点が設置されていた。3人無事に大滝登攀終了、寒さのため一息つく暇なく、硫黄岳に向かう。陽が当たる箇所まで来ると、寒さがいくらか和らぐ。

稜線手前の岩場の切れ目から硫黄岳山頂へ飛び出る。

C隊は、赤岳鉱泉で首を長くしているのではと思い、少し急ぎ気味で下山路を辿った。
(記 なべたけ)