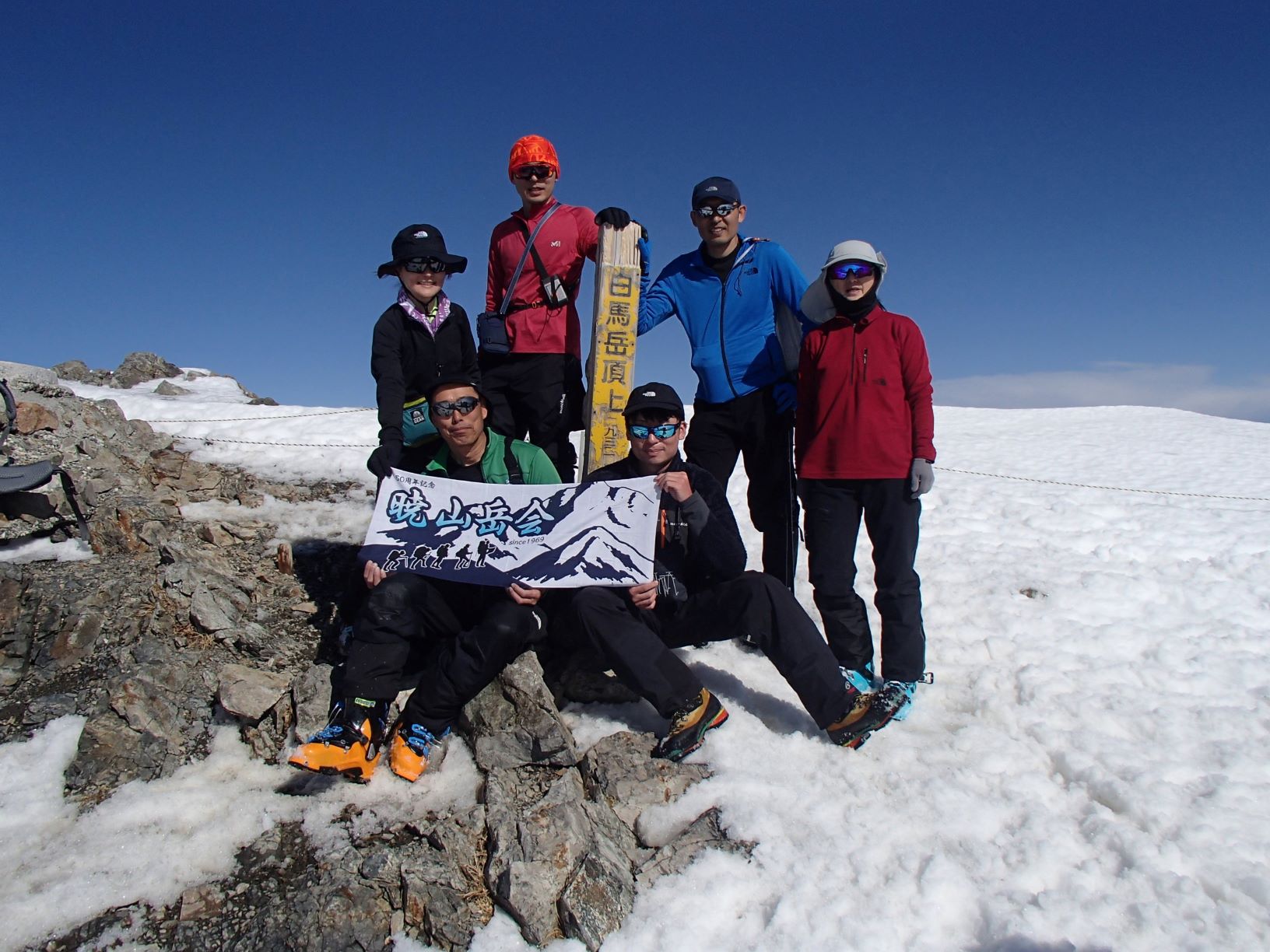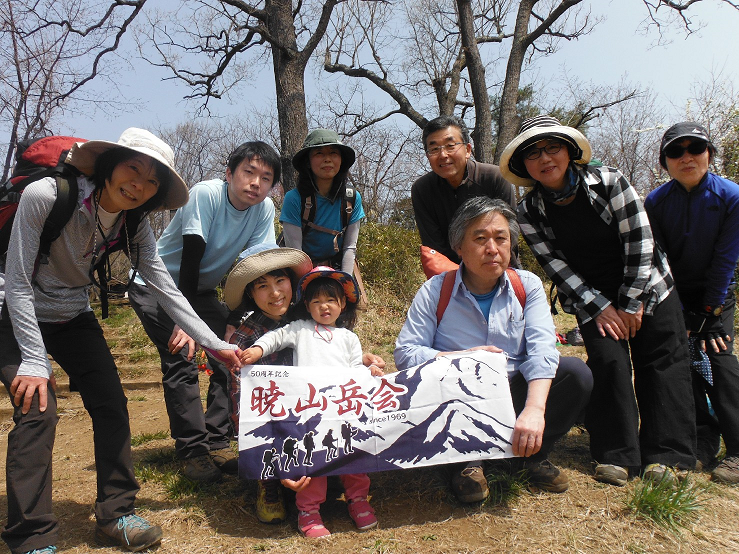期 日:2019年5月5日(日)
参加者:そうべぇ
5月5日(日)
ヤビツ峠(8:30)-塔ノ岳(11:20~11:35)-丹沢山(12:18~12:25)-蛭ケ岳(13:33~13:40)-姫次(14:34~14:40)-焼山登山口バス停(16:28)
丹沢山塊は春から夏にかけて「ヤマビル」シーズンである。あの得体の知れない生き物は人知れず忍び寄り血を吸うのだ。考えただけでもゾッとする。私は嫌いである。「ヤマビル」が活発に活動するシーズン前に丹沢山塊はかたづけておきたかったのだが、活動真っ盛りのシーズンの山行となってしまった。
今回の山行の特徴は、「時間との勝負」。焼山登山口バス停の最終バスは16時38分。これを逃すと、タクシーに頼るかまたは歩いて三ケ木バスターミナルまで歩く事になる。これは何としても避けたい。このコースは1泊2日の山行が一般的であり、日帰りでの縦走、しかも制限時間がある事は非常にリスキーなのだ。マラソンならば制限時間に通過できなければランナー回収用のバスが来て、楽にゴールまでたどり着く事が出来るのだが、山ではそうはいかない。そのため制限時間を設け大倉尾根を下山するエスケープルートを用意した。制限時間は「丹沢山に12時00分」までと決めた。スタート地点となるヤビツ峠までは、秦野駅からバスで向かう。時刻表で調べると秦野駅7時44分発、ヤビツ峠には8時32分着。秦野駅ではたくさんの登山客が列をなしバスを待っていた。バスは次から次へとやってくる。「なぜ?」「そっかー!!」今はゴールデンウィーク中の春山シーズンなのだ。バスは臨時便がありしかも増発されていた。知っていればもう1時間早く行動できたのだが、あとの祭りである。
8時30分にヤビツ峠をスタートした。ゆっくりと急がず、抑え気味に歩き始めた。スタミナ切れが最大の敵。時間を気にして体が出来上がっていないうちに心拍数を上げてしまうと、血液中の乳酸値が高くなりバテの原因となってしまうからだ。そして水分補給。
ニノ塔、三ノ塔と順調に過ぎ、烏尾山あたりではフルモードとなっていた。煽りながらの山行をしているわけではないのだが、前を行く登山者たちが次々と道を譲ってくれる。飛ばしているなと思う登山者にもあっという間に追いつき、しばらくは後をついて登るも、そのうちに道を開けてくれた。いやらしい登山をしているなと少し反省した。塔ノ岳には11時20分に到着、少しの休憩を挟み出発した。

12時を過ぎてしまうが丹沢山まで1時間でいけたらそのまま行動を続けようと思った。12時18分に丹沢山に到着。蛭ケ岳までのアップダウンは絶望的な遠さに思えた。本当に行けるのだろうかと考えてしまう。疲れも出ていたが、躊躇せず先に進んだ。恐ろしいほどのアップダウンを繰り返し、蛭ケ岳が近づいてくる。その向こうには富士山。蛭ケ岳は近づいてくるが、富士山は近くには来ない。大きな山だとつくづく思う。

蛭ケ岳を13時33分に通過、姫次へと向かう。もうこのころからほとんど登山者には出会わなかった。姫次までの登山道は少々荒れているのかなと思った。それに比べ人気の塔ノ岳までのルートは幾つもあるが、ヤビツ峠からのコースや大倉尾根のコースは整備されていると思う。姫次には14時34分到着、少しの休憩を挟みすぐに出発した。ここからは緩やかな下りの連続となるので、かなり走れる。まだ走る体力は残っていたのでありがたかった。最終バスまで2時間を切っている。「走れるだけ走ろう」と思いスタートした。でも転んで怪我をしてもしょうがないので、「走れるところだけ走る」ようにした。 黍殻山を過ぎたところで外国人女性のハイカーに出会った。突然出会ったので驚いてしまった。大きなザックを背負い、この時間に一人で山に登っていたのである。話を聞くと、オーストラリアから遊びに来たようだ。東京から大阪までハイキングしながら旅をしているとのこと。1ヶ月前に東京につき、これから3ヶ月かけて大阪まで徒歩で向かうらしい。そして今日はビバークするとのことで、どこかビバーク地はないかと尋ねられた。一人用のテントは持っているとのこと。近くに黍殻避難小屋があることを教えた。日本ブームなんでしょうか、たくましいなと思った。避難小屋まで案内してあげたかったのだが、私は時間との勝負中であったので、少しの会話で別れた。なだらかな下りを走った。北斜面なので、陽が当たらないと薄暗く、慎重に走った。16時28分に無事に焼山登山口バス停前に到着した。バス到着10分前だった。

体力的にも充実し、時間との戦いのためそれなりに緊張もあり、全てにおいて楽しい山行だった。
(記 そうべぇ)